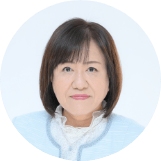「健康には気を付けているし、まだまだ若いつもりだけれど、生活習慣病に備える保険に加入する必要はあるのだろうか」 そのような疑問を持つ方向けに、この記事では生活習慣病保険に加入するメリット・デメリット・必要性について解説します。生活習慣病のリスクに備えたいと考えている方は、ぜひ保険選びの参考にしてください。
※記事中で言及している保険に関して、当社では取り扱いのない商品もあります。
目次
生活習慣病とは?
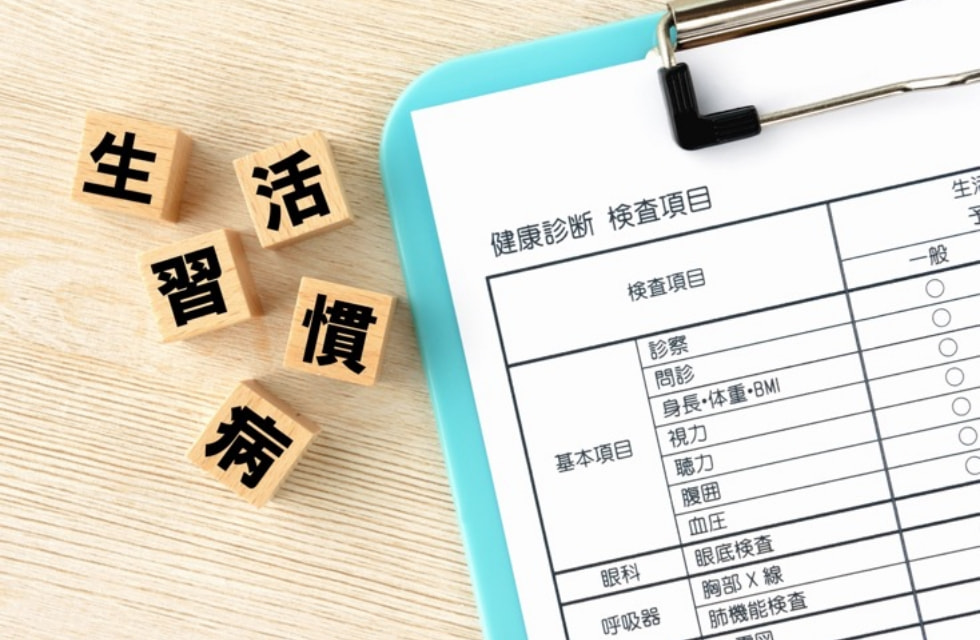
生活習慣病保険への加入を検討する前に、まず生活習慣病とは何かを理解する必要があります。以下で、生活習慣病とはどのような病気なのかわかりやすく解説します。
生活習慣が原因となる病気
生活習慣病とは、加齢に加えて、食事・運動・睡眠・喫煙・飲酒などの生活習慣が発症や進行に関与する病気です。以前は加齢と共に発症・進行すると考えられていたため、「成人病」と呼ばれていましたが、生活習慣の改善により予防が可能であり、成人でなくても発症可能性があることから現在では「生活習慣病」と呼ばれています。
生活習慣病のおもな種類は、以下のとおりです。
- がん
- 心疾患
- 脳血管疾患
- 糖尿病
- 高血圧性疾患
- 肝硬変
- 慢性腎不全
また、高血圧性疾患や糖尿病などの生活習慣病は動脈硬化を進行させ、脳血管疾患や心疾患など別の生活習慣病を誘引する恐れがあります。普段の生活習慣の見直しは、生活習慣病の予防となるだけではありません。生活習慣病によって引き起こされる合併症の予防にもつながります。
生活習慣病を含めた3大疾病・7大疾病とは
「がん」「心疾患」「脳血管性疾患」、この3つの病気を「3大疾病」といいます。3大疾病は、日本人の死因上位を占める重大な病気であり、日本人のおよそ半数の死因を占めます。3大疾病は加齢によってリスクが高まります。そのため、年齢を重ねた人ほど3大疾病に備える保険への加入を検討する必要があります。
そして、3大疾病に「糖尿病」「高血圧性疾患」「肝硬変」「慢性腎不全」を加えたものを7大疾病といいます。7大疾病は7大生活習慣病とも呼ばれますが、生活習慣病と聞くと、著しく不健康な生活を送っている人がかかる病気というイメージを持つ方も少なくないでしょう。ですが、健康に気を付けている人でも、がん・心疾患・脳血管疾患にかかる可能性は低くなく、実際に3大疾病は日本人の死因の上位を占めています。つまり、3大疾病を含む7大疾病は生活習慣に問題がある方だけなく、多くの人にとって向き合う必要がある病気といえるのです。
生活習慣病に備える保険や特約が必要な理由
生活習慣病に備える保険や特約に加入することは、もしもの場合に経済的なサポートが得られるだけでなく、いざという時の金銭的な負担を減らせるというメリットもあります。そこでここからは、生活習慣病に備える保険の必要性について解説します。
3割以上が7大疾病で入院している
入院患者の3人に1人は、いずれかの7大疾病を発症しています。その中でも、特に脳血管疾患は入院が長期化する傾向にあります。入院が長期すれば、治療に必要となる費用は高くなります。
参照:平成29年(2017)患者調査の概況
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kanja/17/dl/01.pdf
3大疾病が日本人の死因上位を占めている
がん・心疾患・脳血管疾患の3大疾病は、日本人の死因上位を占めています。最も多いのはがんで全体の約27.6%、心疾患は約15%、脳血管疾患は約7.5%です。つまり、3大疾病を足すと、日本人の死因の半数程度を占めていることになります。
参照:令和2年(2020)人口動態統計(確定数)の概況
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/kakutei20/dl/11_h7.pdf
生活習慣病での入院は長期化しやすい
生活習慣病で入院する場合には、長期化しやすい傾向があります。入院が長期化すれば、それだけ負担額も増え、医療費もかさみます。
厚生労働省の患者調査によると、平均在院日数はがんで17.1日、心疾患で19.3日、脳血管疾患で78.2日とあります。また、退院後も定期的な通院が必要となる場合には、さらに費用がかかります。
参照:平成29年(2017)患者調査の概況
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kanja/17/dl/03.pdf
生活習慣病の保険・特約に加入するメリット

以下で、生活習慣病の保険・特約に加入する具体的なメリットについて解説します。
7大疾病のリスクに備えられる
7大疾病(7大生活習慣病)は、著しく不健康な生活を送る人だけかかる病気ではありません。それは、食事の好みで糖尿病にかかりやすい人もいますし、加齢によって血圧は高くなりがちということもあります。いずれにしても、入院する人の3割を7大疾病が占めているため、生活習慣病を対象とした保険や特約に加入することで、7大疾病に必要な費用に備えることができます。
治療期間が長くなった場合も安心
生活習慣病の治療によって、入院期間が長くなった場合にも医療保険や医療特約に加入していれば入院給付金や長期入院給付金などが支払われるので安心です。患者の負担額を軽減する国民皆保険制度や高額療養費制度といった制度があったとしても、期間が長くなれば自己負担額は増えていきます。長期の入院に備えるには、生活習慣病の保障が手厚い医療保険や医療特約に加入しておくと安心でしょう。
診断一時金や通院特約でさらに手厚く
生活習慣病での入院が手厚い医療保険や医療特約に加入すれば、従来の医療保険では物足りなかった保障を確保できます。入院保障・手術保障など使途限定ではなく、がん診断・6大疾病一時金など諸費用に充てられる保険を選びましょう。 また、通院特約が付いている保険を選べば、入院前後の通院についても通院給付金を受け取れます。
生活習慣病の保険・特約に加入するデメリット
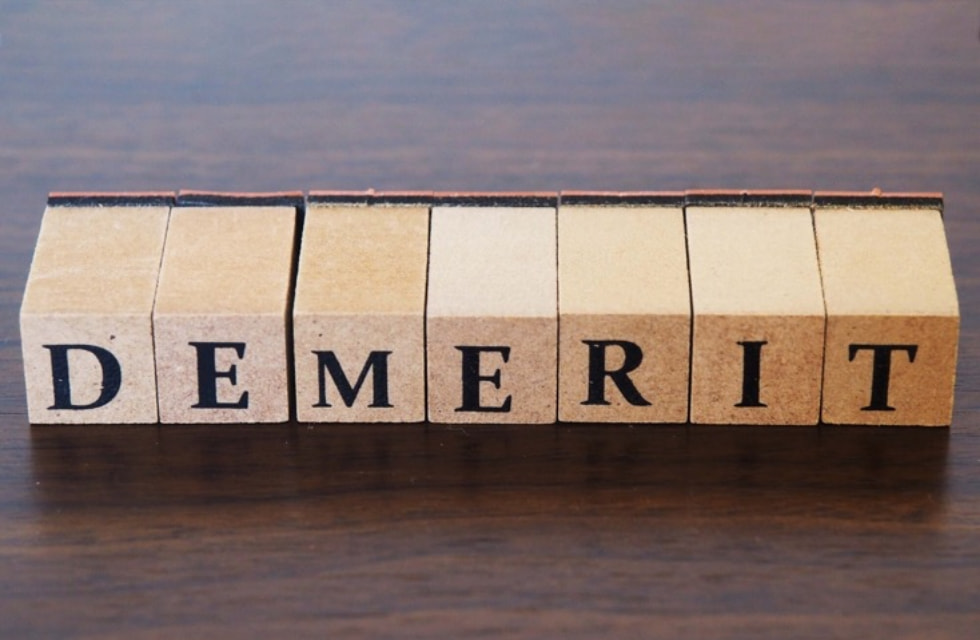
次に、生活習慣病の保険や特約に加入するデメリットについて解説します。
症状が軽い場合には保障が受けられない可能性がある
対象となる病気にかかったとしても、比較的症状が軽い場合には保障が受けられない場合もあります。
例えば、保険の詳細に心疾患の場合には「初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上労働の制限を必要とする状態が続いたと、医師によって診断されたとき」、脳卒中の場合には「初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障害、運動失調、麻痺などの後遺症が継続したと医師によって診断されたとき」などの条件が定められている場合があります。心疾患や脳卒中と診断されたとしても、その後の回復が著しい場合などは、保険金が受け取れないケースもあるわけです。
すべての生活習慣病が対象にはならない
生活習慣病を対象とした保険であっても、すべての生活習慣病が対象になるわけではありません。所定の病気や該当する状態は保険商品によって異なります。定められた条件に該当しなければ保障を受けられないため、加入する前に保障の範囲や条件について、きちんと確認するようにしましょう。
誰もがかかる可能性がある生活習慣病に備える保険に加入しよう
入院患者の3人に1人は7大疾病を患っている現状から、生活習慣病は身近な病気といえるでしょう。身近な病気のリスクに備えて、生活習慣病に備えた保険への加入を検討してみることをおすすめします。
生活習慣病の治療には、入院の長期化や入院前後の通院による治療といった自己負担額の不安が伴います。生活習慣病に備えられる医療保険や医療特約に加入しておくと、自分も家族も安心です。生活習慣病向けの医療保険や医療特約に加入する際は、保証の範囲や給付の条件をよく理解したうえで、保険料負担とのバランスを考えた保険を選びましょう。
article