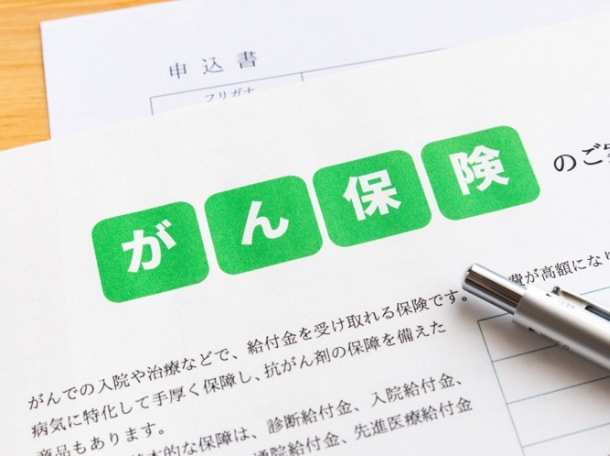がんは日本人の死亡原因1位となる病気です。がんに罹患しないためには、定期的な検診によって健康状態を確認して予防に務めること、そして早期発見によって治療を始めることが重要になります。今回はがん検診の種類や流れなど、基本的な情報について解説します。
参照:令和3年(2021)人口動態統計(確定数)の概況
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/kakutei21/dl/11_h7.pdf
がん検診とは?
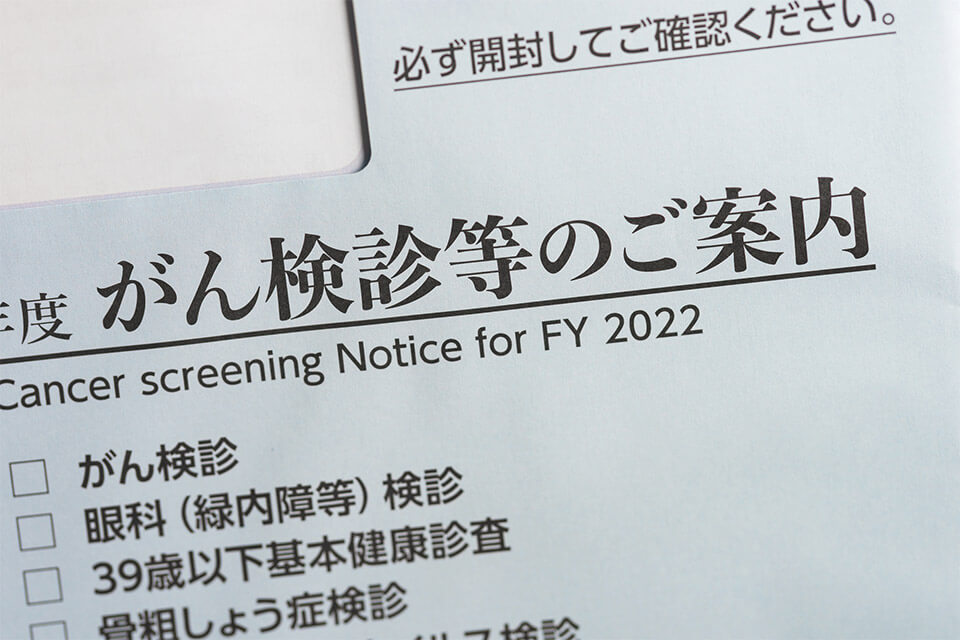
がん検診の目的や方法について解説します。
がん検診の主な目的
がん検診の主な目的は、早期発見・早期治療を実施することで、がんによる死亡を減らすことです。どのような人ががん検診を受けることができるのか、また、検診と健診の違いについても理解しておきましょう。
- 症状のない人が対象
- がん検診の対象者は「がんの症状がない人」に限られます。すでに症状が出ている場合は、検診ではなく、精密検査、そして治療が必要です。早急に医療機関を受診しましょう。
- 検診と健診の違い
- 検診と似た言葉で「健診」があります。それぞれの違いについて解説します。
- 検診 : 特定の疫病を発見するために行われる検査
- 健診 : 特定の疾病ではなく、健康かどうかを確認するための検査(=健康診断)
- がん検診の場合は、特定の疫病「がん」を発見するために行うので、検診という言葉が使われます。
がん検診で実施される検査の手法
がん検診で実施される検査方法としては主に以下の3つがあります。
- 画像検査
- 画像検査には「X線(レントゲン)検査・CT検査・MRI(磁気共鳴画像)検査・PET検査・超音波(エコー)検査」などがあり、がんの有無や広がり、がんの性質を調べるために行われます。
- 病理検査
- 病理検査は、がんなのか?がんであれば、どのような種類のがんなのか?を診断確定するために行われます。採取した細胞や組織を顕微鏡で観察し、良性か悪性かなど、その性質を詳しく調べることができます。
- バイオマーカー検査
- バイオマーカー検査には、がん遺伝子検査・腫瘍マーカー検査といった方法があります。がん遺伝子検査では事前にがんの性質を調べることで治療に用いる薬を選ぶ指標にしています。また、腫瘍マーカー検査は主に腫瘍の量をみるもので、再発や転移がないかなど治療の効果をみるためにも使われています。
参照:がんの検査について それぞれの検査 種類別
https://ganjoho.jp/public/dia_tre/inspection/type.html
がん検診の基本的な流れ
がん検診は以下のような流れで実施されます。

がん検診を受けるとまずは「精密検査が必要か否か」が判断されます。精密検査不要の場合は現時点でがんの疑いがないということになります。要精密検査の場合、がんの疑いがあるため詳しい検査を行い、その後に改めて検査結果が出ます。ここでがんと診断されれば、治療に進むことになります。異常がなかった場合も、定期的にがん検診を受けるようにすることが大切です。
がん検診にはどんな種類がある?

厚生労働省が推奨しているがん検診は以下の5種類があります。これらの検診は「対策型検診」といい、がん死亡率の減少を目的として行われています。市町村などで実施されており、受診者の費用負担は無料かごく少額となっています。
胃がん検診
- 対象者
- 50歳以上
- (※当分の間、胃部X線検査については40歳以上に対して実施)
- 受診間隔
- 2年に1回。
- (※当分の間、胃部X線検査については年1回実施)
- 検査項目
- 問診に加え、胃部X線検査または胃内視鏡検査のいずれか。
子宮頸がん検診
- 対象者
- 20歳以上
- 受診間隔
- 2年に1回。
- 検査項目
- 問診・視診・子宮頸部の細胞診及び内診。
肺がん検診
- 対象者
- 40歳以上
- 受診間隔
- 年に1回。
- 検査項目
- 質問(問診)胸部X線検査及び喀痰細胞診。
乳がん検診
- 対象者
- 40歳以上
- 受診間隔
- 2年に1回。
- 検査項目
- 問診及び乳房X線検査(マンモグラフィ)
- (※視診・触診は推奨しない)
大腸がん検診
- 対象者
- 40歳以上
- 受診間隔
- 年1回。
- 検査項目
- 問診及び便潜血検査。
参照:厚生労働省「がん検診」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000059490.html
がん検診を受けるメリット

がん検診を受けるメリットについて解説します。
- がんを早期発見できる可能性がある
- がん検診の目的でもある、がんの早期発見につながる可能性があるという点が最大のメリットです。がんの早期発見によって、もし罹患していたとしても、完全治癒が望め、また治療にかかる経済的・身体的な負担は軽く済む可能性が高いです。
- がん以外の病気の発見にもつながる
- がん検診によって、対象の部位の精密検査をすることで、がん以外の病気の発見につながることもあります。
- 不安が解消される
- がんは日本人の死亡原因1位になるような病気です。誰でも一度は「もしがんだったら……」と不安になったことがあるのではないでしょうか?がん検診を受けて、異常なしと診断されれば、不安な気持ちは解消され、安心して生活を送ることができますね。ただし、一度受診しただけで安心せず、定期的ながん検診を心がけましょう。
がん検診を受けるデメリット
次に、がん検診を受けるデメリットについて解説します。
- がんを見逃す「偽陰性」の可能性がある
- がん検診の結果は100%正確というわけではありません。がんが小さかったり、見つけにくい場所にあったりする場合は発見できないこともあります。そのため定期的にがん検診を受けることで、がんを発見する可能性を高めることが重要になります。
- 「偽陽性」「過剰診断」になる可能性がある
- 「偽陽性」とは、がん検診で異常が見つかり精密検査を行った結果、がんではないと判明することを指します。また、進行がんにならずに消えてしまうような、生命を脅かさないがんが発見されることがあります。これを「過剰診断」といいます。現在のところ、生命に影響を与えるがんとそうでないものを区別する方法はまだ確立されていないため、本来は不要であったはずの治療や手術を行うことになる点がデメリットとして挙げられます。
がん検診についてのよくある疑問

がん検診についてのよくある疑問について解説します。
がん検診はどこで受けられる?
お住まいの市町村などから委託された医療機関で受けることができます。市町村のホームページなどにがん検診を受けられる医療機関に関しての情報や、実施時期などが掲載されているので確認しましょう。
検診を受けるための準備はある?
胃がん検診・大腸がん検診・肺がん検診などの場合は準備が必要です。
- 胃がん検診:検査当日、検査が終了するまで飲食することはできません。
- 大腸がん検診:検査のために採便を2日実施する必要があります。
- 肺がん検診:重喫煙者(過去の喫煙も含む)の場合、喀痰検査のため3日間喀痰の採取を行います。
検診の身体的な負担の程度は?
検査の種類によっては、不快感や多少の痛みを覚える可能性があります。検査時間としては通常10~20分で完了するものがほとんどですが、場合によっては長くなる可能性があります。
精密検査が必要と言われた場合はどうすれば良い?
がん検診で精密検査が必要と診断された場合は「がんの疑いがある」状態です。症状がないからといって放置してしまうと、本当にがんがあった場合、がんが進行してしまう可能性もあります。必ず精密検査を受け、適切な治療を受けるようにしましょう。
まとめ
がん検診は、がんによる死亡率の減少を目的として行われ、厚生労働省の推奨する5つのがん検診(胃がん検診、子宮頸がん検診、肺がん検診、乳がん検診、大腸がん検診)ではその有効性が確立されています。がん検診を受けることで、がんがある場合は早期発見による治療、がんがない場合は日常生活の不安の解消など、さまざまなメリットがあるので、対象年齢の方はぜひ受診を検討してみてください。
article