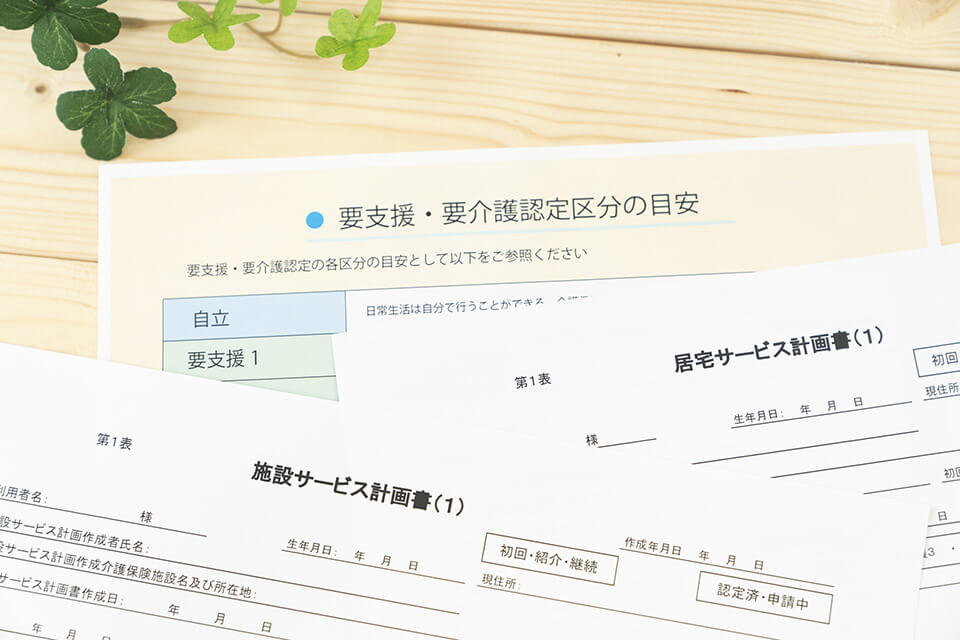
介護が必要になった際に、自己負担1~3割でさまざまな介護サービスを受けられるのが公的な介護保険制度です。今回は、介護保険制度の仕組みやサービス・申請方法について解説します。
目次
介護保険制度とは?概要と仕組み
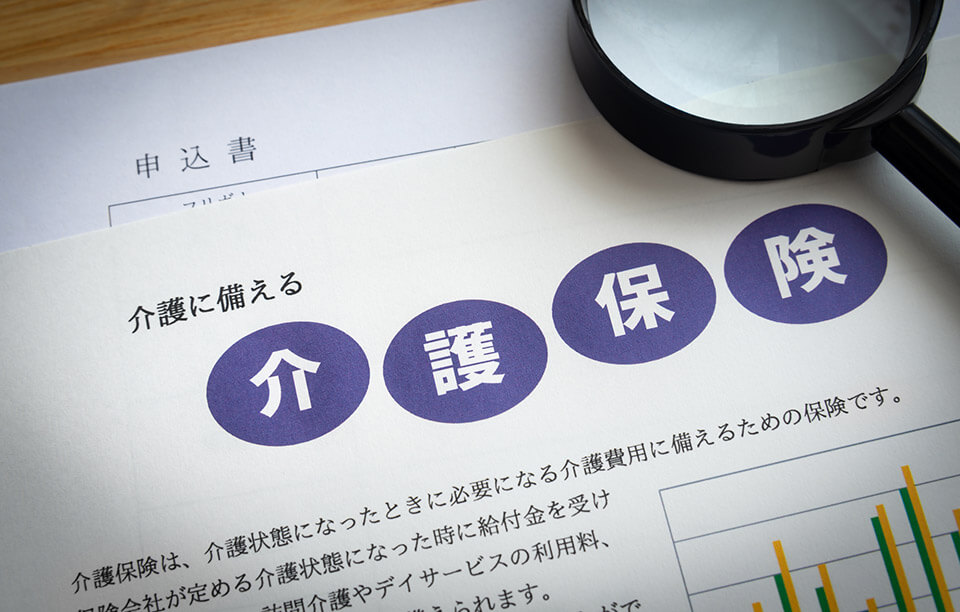
まずは介護保険制度の概要や仕組みについて解説します。
介護保険制度の概要
介護保険制度の基本情報について解説します。介護保険制度は、介護が必要な方に、必要な費用を給付するための制度です。制度の運営は全国の市区町村によって行われています。40歳になると介護保険への加入が義務付けられており、国民から集めた保険料と公費をもとにサービスを展開しています。なお、介護保険制度のサービスを受けるためには、手続きや審査が必要です。
介護保険制度の仕組み
介護保険制度の仕組みは以下のようになっています。
介護保険料について
介護保険制度の被保険者は、「第1号被保険者(65歳以上の方)」と「第2号被保険者(40歳から64歳までの方)」に分類されます。第1号被保険者は、主に年金からの天引きで市区町村徴収され、金額は所得に応じて決まります。第2号被保険者は、加入している健康保険と一緒に介護保険料が徴収され、その金額についても健康保険ごとの算定方法により決まります。
介護保険制度の対象者
保険料の徴収は40歳からスタートしますが、介護サービスの対象者になるのは原則として、第1号被保険者です。ただし、特定の疾病により介護が必要になった場合は第2号被保険者でもサービスを受けることができます。対象となる疾病としては以下があります。
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 脊髄小脳変性症
- 末期がん
- 関節リウマチ
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
介護保険制度でどんなサービスを受けられる?

介護保険制度で受けられるサービスについて解説します。現在公表されているサービスは全26種類54のサービスがあります。その中の一部について解説します。
居宅介護支援
介護保険を使ってサービスを受けるためにはケアプランの作成が必要です。居宅介護支援では、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、ケアマネージャーが利用者の心身の状況や置かれている環境に応じた介護サービスを利用するためのケアプランを作成し、そのプランに基づいて適切なサービスが提供されるよう、事業者や関係機関との連絡・調整を行います。
居宅サービス
自宅に住みながら、以下のようなサービスを受けることができます。
- 【訪問型サービス】
- ・訪問介護
- ・生活援助
- ・身体介護
- ・訪問看護
- ・訪問入浴介護
- ・訪問リハビリテーション
- ・居宅療養管理指導
- ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 【通所型サービス】
- ・デイサービス
- ・デイケア
- ・認知症対応型通所介護
- 【短期滞在型サービス】
- ・ショートステイ(短期入所生活介護、短期入所療養介護)
施設サービス
自宅ではなく、施設に入居して生活をしながらサービスを受けることができます。施設サービスとしては以下のようなものがあります。
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設
- 介護医療院
福祉用具に関するサービス
以下のような福祉用具を借りたり、購入したりすることができるサービスです。
- 福祉用具の貸与
- 特定福祉用具販売
この他にも複数の介護サービスがあります。より詳しく知りたいという方は以下のサイトを参考にしてみてください。
参照:厚生労働省「公表されている介護サービスについて」
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/publish/
介護保険サービスの自己負担額・支給限度額について
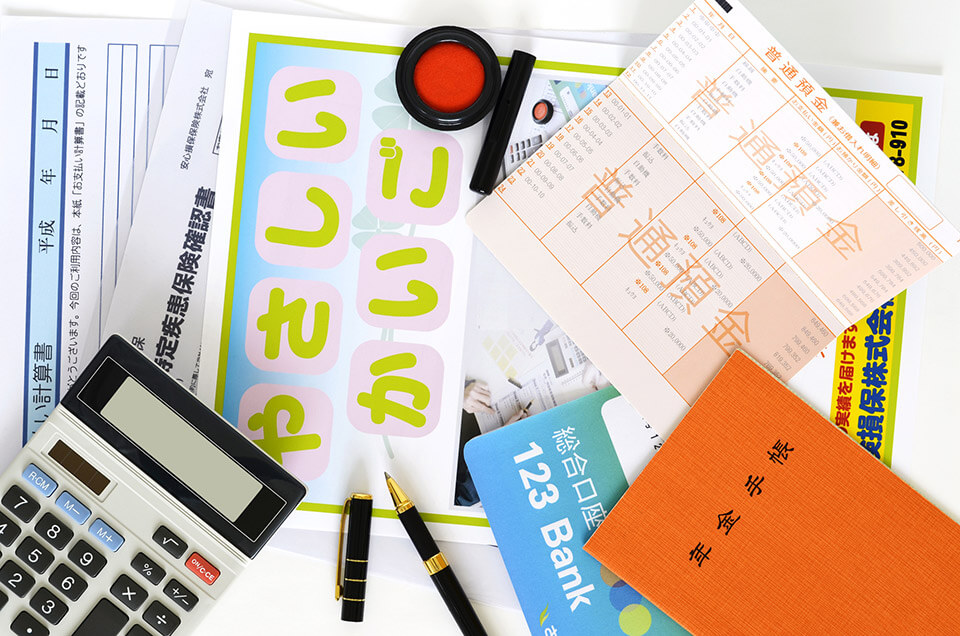
介護保険サービスの自己負担額や支給限度額について解説します。
介護保険サービスの自己負担の割合は?
介護保険サービスの自己負担額は、サービスの利用にかかった費用の1~3割です。要介護度や所得、利用するサービスによって自己負担の割合が変わります。
サービスを利用する場合の自己負担額
居宅サービスを利用する場合は、要介護度によって支給限度額が設定されています。限度額を超えるサービスを追加したい場合は、超過分を自己負担することで利用できます。
居宅サービスの1ヶ月あたりの支給限度額
| 要介護度 | 支給限度額 | 1割負担額 | 2割負担額 | 3割負担額 |
|---|---|---|---|---|
| 要支援1 | 50,320円 | 5,032円 | 10,064円 | 15,096円 |
| 要支援2 | 105,310円 | 10,531円 | 21,062円 | 31,593円 |
| 要介護1 | 167,650円 | 16,765円 | 33,530円 | 50,295円 |
| 要介護2 | 197,050円 | 19,705円 | 39,410円 | 59,115円 |
| 要介護3 | 270,480円 | 27,048円 | 54,096円 | 81,144円 |
| 要介護4 | 309,380円 | 30,938円 | 61,876円 | 92,814円 |
| 要介護5 | 362,170円 | 36,217円 | 72,434円 | 108,651円 |
施設サービスを利用する場合は、施設サービス費のほか居住費、食費、日常生活費が必要になります。所得が低い場合や、1ヶ月あたりの利用料が高額になった場合は負担軽減措置があります。
利用者の負担を軽減する制度について
これらの介護サービスについて、利用者の負担が増えすぎないよう所得に応じて負担を軽減する制度があります。そのうち「特定入所者介護サービス費」では、負担限度額認定を市区町村から受けることで、限度額を超える居住費・食費の負担額が支給されます。例えば、設定区分が第2段階の方(非課税世帯、年金+その他の収入が80万円以下)が特別養護老人ホームを利用する場合、居住費は「多床室1日あたり約370円・個室約420円」、食費は1日あたり約390円と、少ない負担で利用することができます。
参照:厚生労働省「介護保険サービスにかかる利用料」
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/commentary/fee.html
介護保険制度の利用を申請する方法と利用の流れ

介護保険制度の利用を申請する方法と利用する流れについて解説します。
申請に必要な書類
介護保険制度を利用するには、各市区町村の介護保険課、高齢者支援課への申請が必要です。以下の書類を提出・提示すると、認定調査(訪問して面談や身体機能のチェックなど)が行われます。認定調査と主治医の意見書により1次判定→2次判定と進み、要介護・要支援認定についての結果が通知されます。認定までは1か月程度かかることが多いようです。
- 要介護(要支援)認定申請書
- 介護保険被保険者証(第2号被保険者は健康保険の保険証)
- 個人番号が確認できるもの(マイナンバーカードもしくはマイナンバー通知カード)
要介護認定~介護保険利用申請の流れ
要介護認定から、介護保険の利用申請までの流れについて解説します。
- 1.申請書類の提出
- 自治体の介護保険担当窓口に必要書類を提出します。介護保険申請書には「主治医・病院の名前や所在地・最終受診日」などを記載するため、診察券など確認できるものも用意しておきましょう。
- 2.調査員による認定調査・主治医の意見書作成
- 調査員が自宅や施設等を訪問して、申請者の心身の状態や生活状況を確認します。また、かかりつけ医への意見書作成依頼が行われます。
- 3.介護保険の審査判定
- 提出書類と認定調査、医師の意見書を確認して審査判定を行います。審査は、介護認定審査会が行います。申請から判定までは約1か月です。非該当、要支援1~2、要介護1~5のいずれかに分類されます。
- 4.ケアプランの作成
- 要支援・要介護が認定されれば、地域包括支援センターまたは居宅介護支援事業者に、ケアプランの作成を依頼します。介護支援専門員が、申請者と家族の希望や意見を考慮してケアプランを作成します。
- 5.介護保険制度の利用開始
- ケアプランをもとに、介護サービスが受けられるようになります。申請者の健康状態に変化があれば、介護レベルを改めて判定することができます。
介護保険制度の課題と改正について
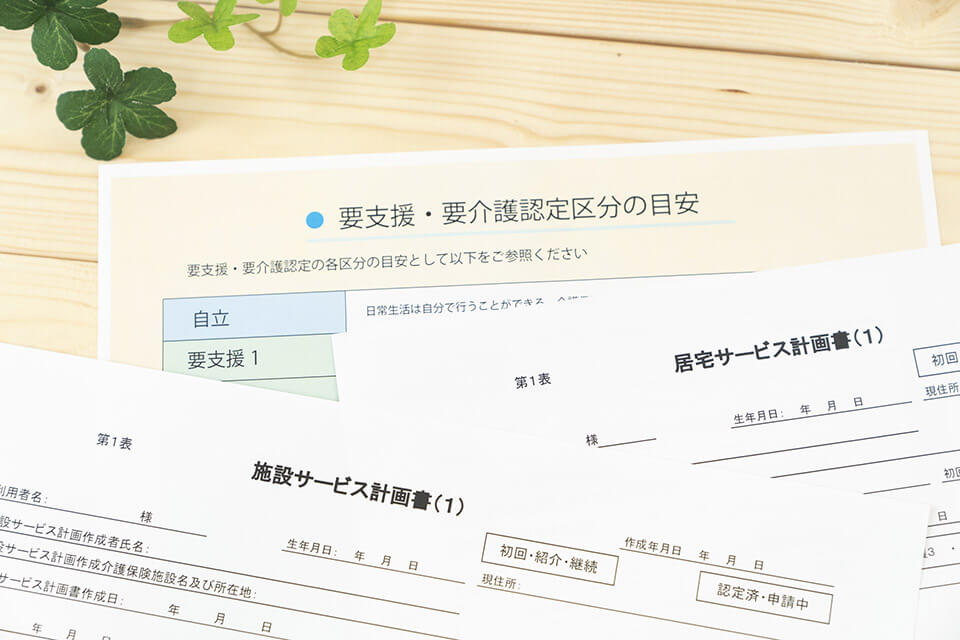
日本では高齢化が急速に進行しています。利用者の増加に伴い、現状の介護保険制度はさまざまな問題に直面しています。介護保険制度の課題や今後について解説します。
介護保険制度が抱えている課題
団塊の世代が75歳以上になる2025年までは、介護サービスのニーズが急増すると考えられています。それに伴って、財源不足・人手不足が深刻化すると予想されています。また、2040年になると現状の制度を支えている世代が大幅に減少するといわれており、制度自体をどのように維持するかという課題も抱えています。
制度改正の頻度と内容について
このような変化に対応するため、介護保険制度は3年ごとに見直されます。第1号被保険者の1人当たり月額保険料の全国平均は第一期(2000~2002年)の2,911円から第八期(2021~2023年)には6,014円まで上昇しました。また、今後は介護人材の確保のため、介護職員の処遇改善などが行われると予想されています。
地域包括ケアシステムについて
高齢者が住み慣れた町で自分らしい暮らしを長く続けられるように、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される「地域包括ケアシステム」の構築が推進されています。高齢者人口の増減スピードなどによって高齢化の進展状況には大きな地域差があり、認知症高齢者の地域での生活を支えるためにも地域包括ケアシステムの構築が重要となっています。
参照:厚生労働省「介護保険制度をめぐる最近の動向について(第92回社会保障審議会介護保険部会)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24727.html
まとめ
介護保険制度とは、介護度に応じて自己負担1~3割で介護サービスを受けるための制度です。40歳になると介護保険への加入が義務になるため、仕組みやサービスについてわからないという方は今回ご紹介した内容を参考に、制度の概要を掴んでおきましょう。また、自分や家族が介護保険を利用する際に備えて、制度の利用方法や手続きも確認しておいてください。
article









