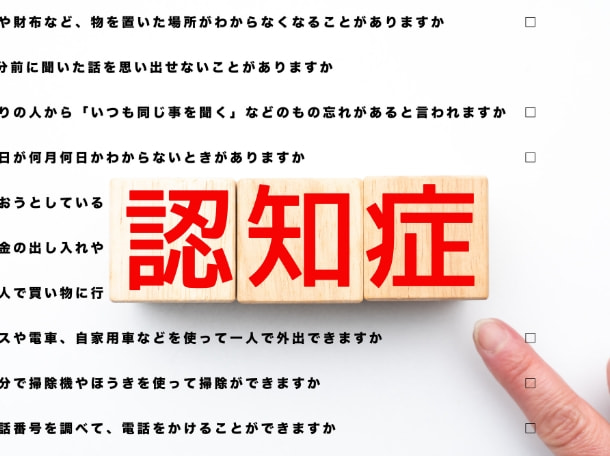高齢者の半数近くが単身世帯である現代において、認知症の方が一人暮らしをすることによるリスクについては、今後社会全体で考えなければならないテーマといえるでしょう。認知症の方が一人暮らしをする場合のリスクやトラブルの予防方法などについて詳しく解説します。
目次
高齢者世帯(65歳以上のみの世帯または18歳未満の未婚の者と同居)の約半数は単身世帯
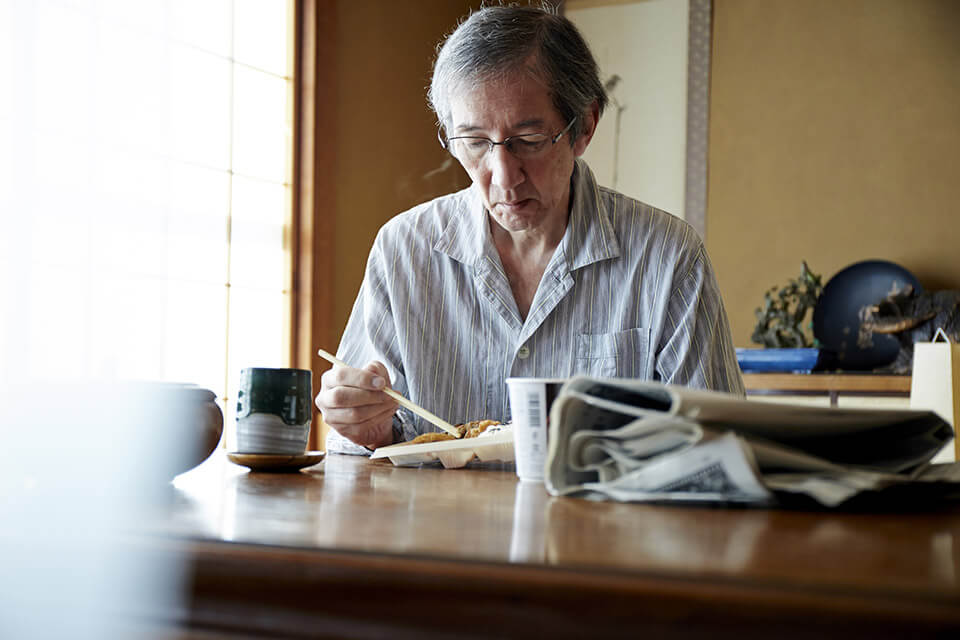
内閣府が発表した令和4年版「高齢社会白書」によると、令和3年10月1日時点の高齢化率は28.9%です。日本人の約4人に1人が高齢者になる計算で、今後もこの数は増え続けることが予想されています。
また、厚生労働省が発表した2021年「国民生活基礎調査の概況」によると、高齢者の「単独世帯」が742万 7千世帯で高齢者世帯(65歳以上のみの世帯または18歳未満の未婚の者と同居)の49.3%を占めており、半数近くを一人暮らしが占めているということがわかります。
参照:
内閣府 令和4年版「高齢社会白書」
https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2022/zenbun/04pdf_index.html
厚生労働省 2021年「国民生活基礎調査の概況」
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa21/index.html
認知症の高齢者が一人暮らしをするリスクとは?

次に認知症の高齢者が一人暮らしをするリスクについて解説します。以下のようなリスクがあると考えられます。
火の不始末による火災のリスク
認知症は比較的軽度の段階から、物忘れや注意力が低下することで知られています。物忘れや注意力低下で発生する最大のリスクは「火の不始末」による火災です。コンロの切り忘れ、タバコの不始末、洗濯物をこたつやヒーターで乾燥を試みる、暖房器具の不始末などによって火災が発生すると、本人はもちろん集合住宅の場合は周囲の人間にも被害が及んでしまう可能性もあります。
外出時の事故や行方不明
認知症の症状のひとつとして見当識障害があります。見当識障害では自分の置かれている状況が正しく認識できず、外出したまま家に帰れなくなってしまうなど、行方不明や事故に遭うリスクが高くなります。
食生活の乱れによる健康状況の悪化
認知症が進行すると、料理をするのがおっくうになったり、上手くできなくなったりすることがあります。すると食生活も乱れがちになり、栄養バランスが偏って健康状態の悪化につながります。また、食品の管理が出来なくなる(賞味・消費期限が切れている食品やカビが生えて腐った食品を食べてしまうことも)ことや調理行程がわからなくなってしまう(加熱が必要な食品を生で食べてしまう、焦げた物を食べるなど)点にも注意が必要です。
服薬管理が難しい
一人暮らしの認知症患者で困難になるのが服薬管理です。持病を抱えている場合、習慣的に服薬ができなくなったり、過剰に服薬をしてしまったりするリスクが発生します。
金銭トラブル
記憶力・判断力の低下により、金銭管理が正常にできなくなってしまうことがあります。同じものをいくつも買ってしまったり、「物盗られ妄想」によって、お金を盗まれたと思い込んだりするなど、お金に関するトラブルが発生しやすくなります。
親が一人暮らしになる前に。トラブルを予防する方法

認知症の高齢者が一人暮らしをすると、さまざまなトラブルにつながる可能性があります。自身の親が一人暮らしになる可能性がある場合は、トラブルを予防するために以下のポイントを抑えておきましょう。
資産・体調・服薬などの状況を把握する
一人暮らしになる場合は、事前に親の資産・体調・持病・服薬の有無などの情報を整理して理解しておきましょう。特に資産と服薬に関しては、親だけが管理できる状態ではなく、一緒に状況を把握できるようにしておくことが大切です。そうすれば、資産が極端に減ってないか、しっかり服薬ができているかなどを随時確認でき、トラブルに気付きやすくなります。
人との繋がりを作る
一人暮らしの親が認知症になってしまった場合、家族だけで介護をするには限界があります。親だけでなく、介護者の負担も減らすためには、親が住んでいる地域の人とのつながりを増やすことが必要です。近所付き合いがあれば、異変に気付く可能性が高くなり、深刻なトラブルを未然に防ぐこともできます。また、自治体によっては65歳以上で要介護(支援)の方へ自宅に緊急通報装置を設置し、ボタンを押すだけで地域包括支援センターへ連絡が行くようなシステムがあります。このような自治体単位の支援を受けることも検討してみましょう。
兄弟姉妹・親戚と介護を分担する
親が認知症などで介護が必要になった場合、1人ですべての世話を行うのは非常に困難です。負担を分散するために、兄弟姉妹・親戚と話し合い、訪問の頻度や順番をあらかじめ決めておき、誰か1人に負担がかかりすぎないように注意しましょう。
何かを決める際には必ず本人の意見を尊重する
生活に関わることで、何かを決める際には必ず本人の意見を尊重するようにしましょう。親のためになるからといって、勝手に物事を決めてしまうのはNGです。本人の意志を尊重することで、必要な支援に関しての話を聞いてもらえたり、受け入れてもらいやすくなったりすることもあります。
認知症介護について相談できる場所を見つける
親が認知症になってしまい戸惑っている、自分ではどうしたらいいかわからないという方は信頼できる相談相手を見つけることが大切です。地域包括支援センターや自治体の窓口など身近な場所でも相談することができるので、まずは足を運んでみましょう。
- 地域包括支援センター
- 自治体・社会福祉協議会等の相談窓口
- 医療機関での相談(かかりつけ医)
- 親の介護経験がある知り合い
認知症の一人暮らしで頼りになるサービスは?

最後に、認知症の一人暮らしで頼りになるサービスについて解説します。家族だけでの介護には限界があるため、必要に応じて以下のようなサービスを活用しましょう。ここでは介護保険が適用されるサービスについてご紹介します。
介護保険サービスとは?
介護保険が適用され、利用料を一部負担で使えるサービスです。利用者の負担額は1割~3割で収入により変動します。要支援・要介護認定を受けている方に限り利用できます。
介護保険ではどんなサービスを受けられる?
介護保険が利用できるサービスには以下のようなものがあります。
- 介護サービスの利用にかかる相談、ケアプランの作成
- 自宅で受けられる家事援助等のサービス
- 施設などに出かけて日帰りで行うサービス
- 施設などで生活(宿泊)しながら、長期間又は短期間受けられるサービス
- 訪問・通い・宿泊を組み合わせて受けられるサービス
- 福祉用具の利用にかかるサービス
参照:厚生労働省「公表されている介護サービスについて」
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/publish/
介護保険が利用できるサービス一覧
介護保険が利用できるサービスの中から代表的なものをご紹介します。
- 【介護相談やケアプランの作成に関わるサービス】
- ・居宅介護支援
- など
- 【自宅で受けられるサービス】
- ・訪問介護(ホームヘルプ)
- ・訪問入浴
- ・訪問看護
- ・訪問リハビリ
- ・夜間対応型訪問介護
- ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- など
- 【施設に日帰りで通って受けられるサービス】
- ・通所介護(デイサービス)
- ・通所リハビリ
- ・地域密着型通所介護
- ・療養通所介護
- ・認知症対応型通所介護
- など
- 【施設での宿泊を含むサービス】
- ・小規模多機能型居宅介護
- ・看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)
- ・短期入所生活介護(ショートステイ)
- ・短期入所療養介護
- ・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- ・介護老人保健施設(老健)
- ・介護療養型医療施設
- など
- 【福祉用具の貸出や購入に関わるサービス】
- ・福祉用具貸与
- ・特定福祉用具販売
- など
この他、全26種類54のサービスがあります。詳しく確認したい方は厚生労働省の以下のサイトを確認してみてください。
参照:厚生労働省「公表されている介護サービスについて」
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/publish/
まとめ
認知症の高齢者が一人暮らしをする場合にはさまざまなリスクがあります。深刻なトラブルに発展することのないよう、事前に対策を行っておくことが大切です。親が認知症になっている、一人暮らしになる可能性がある、すでに一人暮らしをしているといった方は、今回ご紹介したトラブルの例や対策を参考にしてみてください。
article